A05研究項目
A05-1 超適応現象を適切に強化する閉ループ脳刺激法
研究概要

竹内 雄一
脳内ネットワーク再編は適切に生じた際は障害の回復など好ましく働くが、一方不適切に生じた際は障害が回復しないまたは例えば幻肢痛のような病態に陥るなど好ましくない結果を生じる。しかしながらこれまで脳内ネットワーク再編を適切に強化・誘導する手法は乏しかった。そこで本研究では、遷移する脳内ネットワークダイナミクスの好ましい状態を実時間検出して時間特異的に報酬系脳領域を刺激することで、脳機能障害の回復につながる脳内ネットワーク再編を適切に強化・誘導する手法を開発する。
研究組織
| 研究代表者 | 竹内 雄一 | 北海道大学 大学院薬学研究院 准教授 |
| 研究協力者 | チャン ミシェル | 北海道大学 大学院薬学研究院 特任助教 |
A05-2 脳卒中患者の上肢回復過程における使用行動-身体意識-脳の変容機構の包括的理解
研究概要

出江 紳一
本研究では、亜急性期脳卒中患者を対象とし、上肢回復過程における脳の機能・構造ネットワークの可塑的変化を安静時fMRI・DTIを用いて縦断的に計測する。また、上肢使用頻度と身体特異性注意をそれぞれ加速度計と心理物理的手法を用いて計測し、これらの因果関係と神経基盤を解明する。脳卒中上肢麻痺のリハビリテーションにおける超適応を神経基盤の観点で深掘りし、本領域における行動遂行と神経再構築の関係の解明に貢献することを目指す。
研究組織
| 研究代表者 | 出江 紳一 | 東北大学 医工学研究科 教授 |
| 研究協力者 | 関 慎太郎 | 東北大学 大学院医学系研究科 非常勤講師 |
| 大瀧 亮二 | 東北大学 大学院医学系研究科 博士課程学生 | |
| 須藤 珠水 | 大内病院 研究員 東北大学 大学院医学系研究科 非常勤講師 |
|
| 石母田 竜子 | 東北大学 大学院医学系研究科 研究事務担当者 | |
| 会津 直樹 | 藤田医科大学 保健衛生学部 助教 | |
| 呉 娟 | 東北大学 大学院医学系研究科 大学院生 | |
| 安宅 航太 | 東北大学 大学院医学系研究科 大学院生 |
A05-3 外部環境への適度な適応を実現する神経回路の解明
研究概要

木村 梨絵
外部環境にやみくもに過度に適応したり、全く適応できなかったりすると、心身に不調をきたし、多くの場合、生活の質は低下する。“適度に適応する”ことが生活の質を高める上で重要になると考えられる。視覚弁別課題を遂行するラットやマウスを用いて、視覚刺激のコントラストの変化に対する入力-出力変換の適応が、ストレス負荷や発達障害の特性によってどのように修飾されるかを明らかにする。多脳領野間の多次元脳システムの視覚応答を調べることで、外部環境への“適度な適応”の神経基盤の理解を目指す。
研究組織
| 研究代表者 | 木村 梨絵 | 東京大学 国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任助教 |
A05-4 適応行動を司る脳の単一学習則の提案と神経基盤検証
研究概要
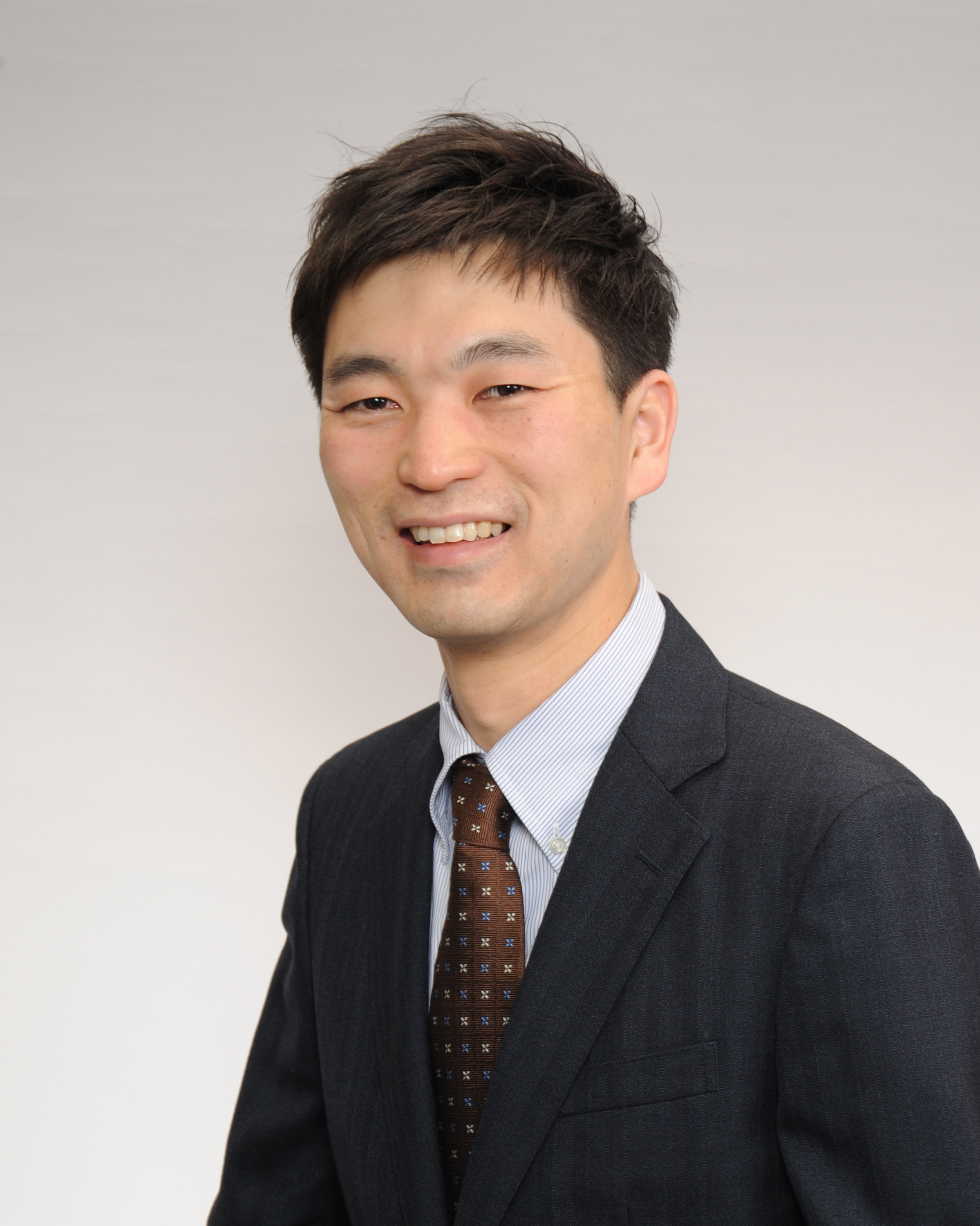
船水 章大
じゃんけんを例に,私達の意思決定や行動選択を考えてみましょう.私達は,自分の定番の一手を出したり,相手の手を読み次の 一手を決めたりと,様々な戦略を脳内で保持し,行動を選択します.脳は複数の学習則を独立に保持しているのでしょうか.それとも,脳には単一の学習則が存在し,複雑な神経回路で行動を決定しているのでしょうか.本研究は,マウスの行動実験や神経活動操作と計測,人工神経回路網 (人工知能:AI)での行動モデル化で,脳の行動戦略様式を検証します.本研究の達成は,脳の柔軟な適応行動の神経基盤解明に繋がります.将来は,脳型人工知能の構築に貢献したいと考えています.
研究組織
| 研究代表者 | 船水 章大 | 東京大学 定量生命科学研究所 講師 |
| 研究協力者 | Maria Ines de Sa Ribeiro | 東京大学 定量生命科学研究所 技術補佐員 |
A05-5 幼少期の多様な経験に基づく過剰な神経回路形成による加齢後の適応能力の拡大
研究概要

杉山 陽子(矢崎 陽子)
発達臨界期には環境からの入力に依存して神経回路を形成され、この神経回路により高次機能発達、成長後の機能が制限されることが知られている。また幼少期の多様な経験が“過剰に“神経回路を形成し、この過剰な神経回路が加齢後の環境変化や機能損傷といった変化に対する適応能力を増大するシステムが報告されている。
ヒトが言語発達と同様、歌を学習するトリ、ソングバードも発達期に親の歌を聞き覚え、これを模倣することで歌を学習する。私達はキンカチョウを用い、親の歌の記憶が高次聴覚野に形成されること、この記憶に関わる細胞が発達期にのみ発声学習に関わる運動野に神経投射することを見出した。さらに最近の研究から、発達期に異なる歌を再学習すると、それぞれの記憶に関わる神経細胞が運動野に神経投射し、さらに成長後もこの学習神経回路を維持する可能性を示唆した。本研究では発達期の多様な学習経験による過剰な神経回路形成の神経メカニズムを明らかにし、さらに成長後の学習機能回復を目指す。
研究組織
| 研究代表者 | 杉山 陽子(矢崎 陽子) | 沖縄科学技術大学院大学 臨界期の神経メカニズム研究ユニット 准教授 東京大学 ニューロインテリジェンス国際研究機構 特任准教授 |
A05-7 ヒト高次運動機能の超適応:皮質脳波コネクトミクスによる脳切除後の潜在回路の解明
研究概要

松本 理器
運動関連領域を外科切除する場合に道具使用を含めた行為等の高次運動障害が残存するか回復するかを術前に予測するのは困難であり、脳領域だけでなく領域間の結合も含めたネットワークの理解が不可欠である。前回の公募研究では網羅的な低頻度電気刺激による因果的結合解析から皮質脳波コネクトームを作成し、高次脳機能を有する皮質におけるネットワークの構造上の特徴を示してきた。本研究では皮質切除後の高次運動障害の有無や回復の程度にはネットワークの構造上の特徴が関与していると考え、障害からの回復(超適応)過程には通常では使用されていない回路(潜在回路、代替回路)が活性化し、ネットワーク構造で潜在回路の活性化が示唆される場合には回復が起こりやすいのではないかという仮説を立てた。これまで我々が作成してきた皮質脳波コネクトームのデータベースを用いて、脳切除前後のネットワークの構造上の変化をシミュレーションし、グラフ理論等の構造指標の変化を定量化する。術前後でのこれらの指標の変化の多寡と症状発現や回復の程度との連関を明らかにし、個人ごとのネットワークの構造上の違いによる機能障害の出現、回復を予測することを目的とする。
研究組織
| 研究代表者 | 松本 理器 | 神戸大学 大学院医学研究科 教授 |
| 研究協力者 | 篠山 隆司 | 神戸大学 大学院医学研究科 教授 |
| 藤本 陽介 | 神戸大学 大学院医学研究科 助教 | |
| 十河 正弥 | 神戸大学 大学院医学研究科 助教 | |
| 的場 健人 | 神戸大学 大学院医学研究科 助教 | |
| 菊池 隆幸 | 京都大学 大学院医学研究科 講師 | |
| 下竹 昭寛 | 京都大学 大学院医学研究科 助教 | |
| 宇佐美 清英 | 京都大学 大学院医学研究科 助教 | |
| 武山 博文 | 京都大学 大学院医学研究科 客員研究員 | |
| 木村 正夢嶺 | 神戸大学 大学院医学研究科 大学院生 | |
| 林 梢 | 京都大学 大学院医学研究科 大学院生 |
A05-8 恐怖記憶に起因する不適応状態からの超適応を誘起する脳領域間ネットワーク動態の解明
研究概要

宮脇 寛行
動物は強い恐怖をともなう記憶により動物は適切な行動が取れなくなる不適応状態へと陥るが、その後の消去学習が引き起こす超適応により適応的な行動を回復する。研究代表者らはこれまでに、自由に行動しているラットからの多領域同時・大規模電気生理学記録法を用い、不適応状態への遷移によって脳領域横断的な同期活動が新たに生じるようになることを明らかにしてきたが、不適応状態からの超適応によりどのような変化が誘導されるのかは未だに不明である。そこで本研究課題では大規模電気生理学、光遺伝学、動物行動学を駆使し、超適応がどのような脳領域間ネットワーク変化を誘導することで達成され、その変化がどのように制御されているかを明らかにする。
研究組織
| 研究代表者 | 宮脇 寛行 | 大阪公立大学 大学院医学研究科 講師 |
A05-9 主体感(Sense of Agency)の精度向上のための認知リハビリテーションの開発と臨床応用
研究概要

前田 貴記
神経疾患・精神疾患において異常な状態にある心身機能を「回復」させるために、主体の意識・アウェアネスのレベルからトップダウンに神経系にはたらきかけ、神経系の再編成を通じて、心身機能の超適応を促通する方法の確立を目指す。具体的アプローチとして、「主体感:Senseof Agency(SoA)」の精度を向上させるための認知リハビリテーション方略(Agency Tuning)を開発し、将来的な介入研究の基盤研究として、臨床研究を進めている。主体感という、人間が環境に適応して生きていくための基盤となる意識・アウェアネスの精度を向上させることにより、疾患・病態横断的に心身機能の「回復」がみられることが期待される。
研究組織
| 研究代表者 | 前田 貴記 | 慶應義塾大学 医学部 講師 |
| 研究協力者 | 山下 祐一 | 国立精神・神経医療研究センター 神経研究所 室長 |
| 沖村 宰 | 慶應義塾大学 医学部 | |
| 大井 博貴 | 慶應義塾大学 医学部 |
A05-10 「超適応」を引き起こす神経回路の生成と解明
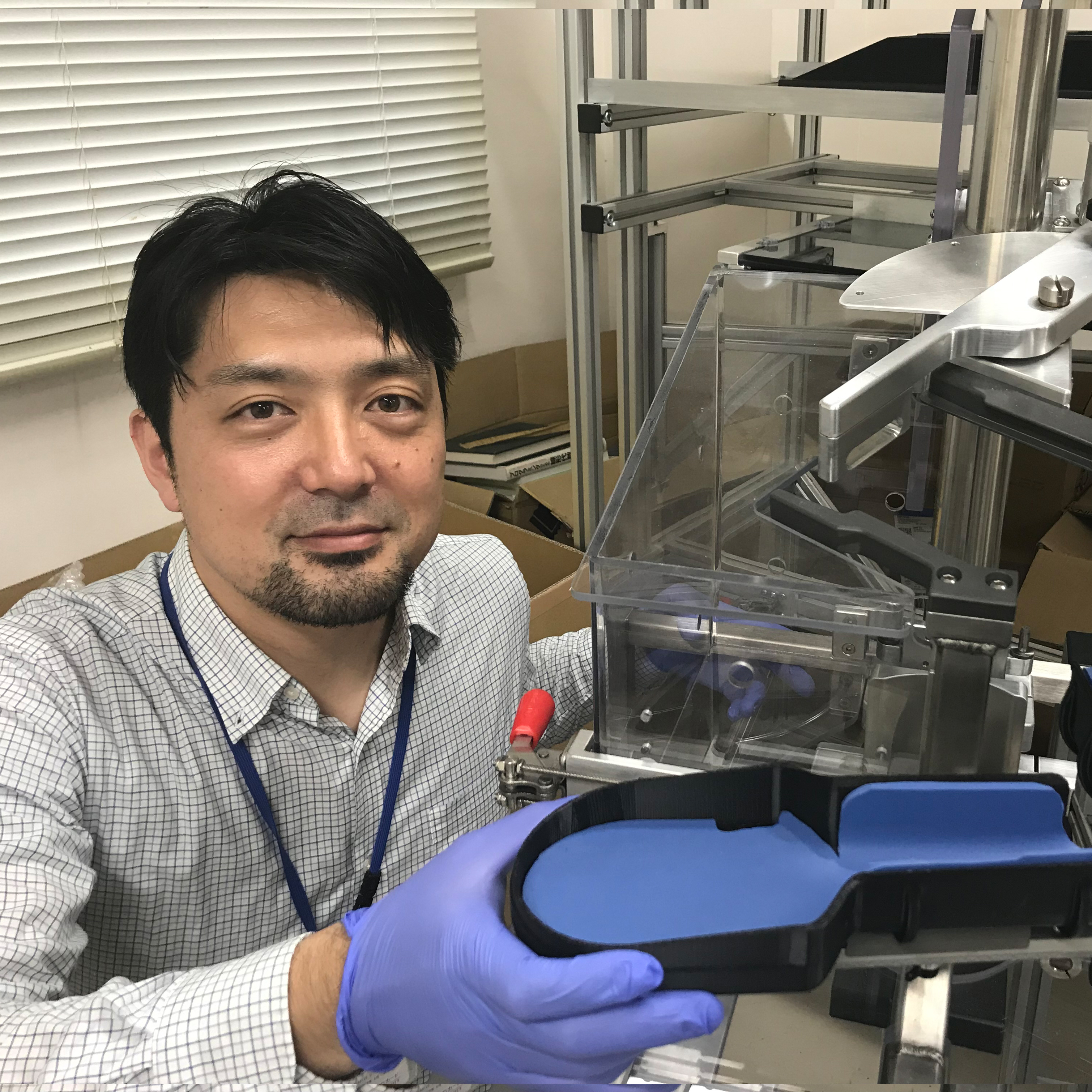
A05-10 研究代表者
武井 智彦
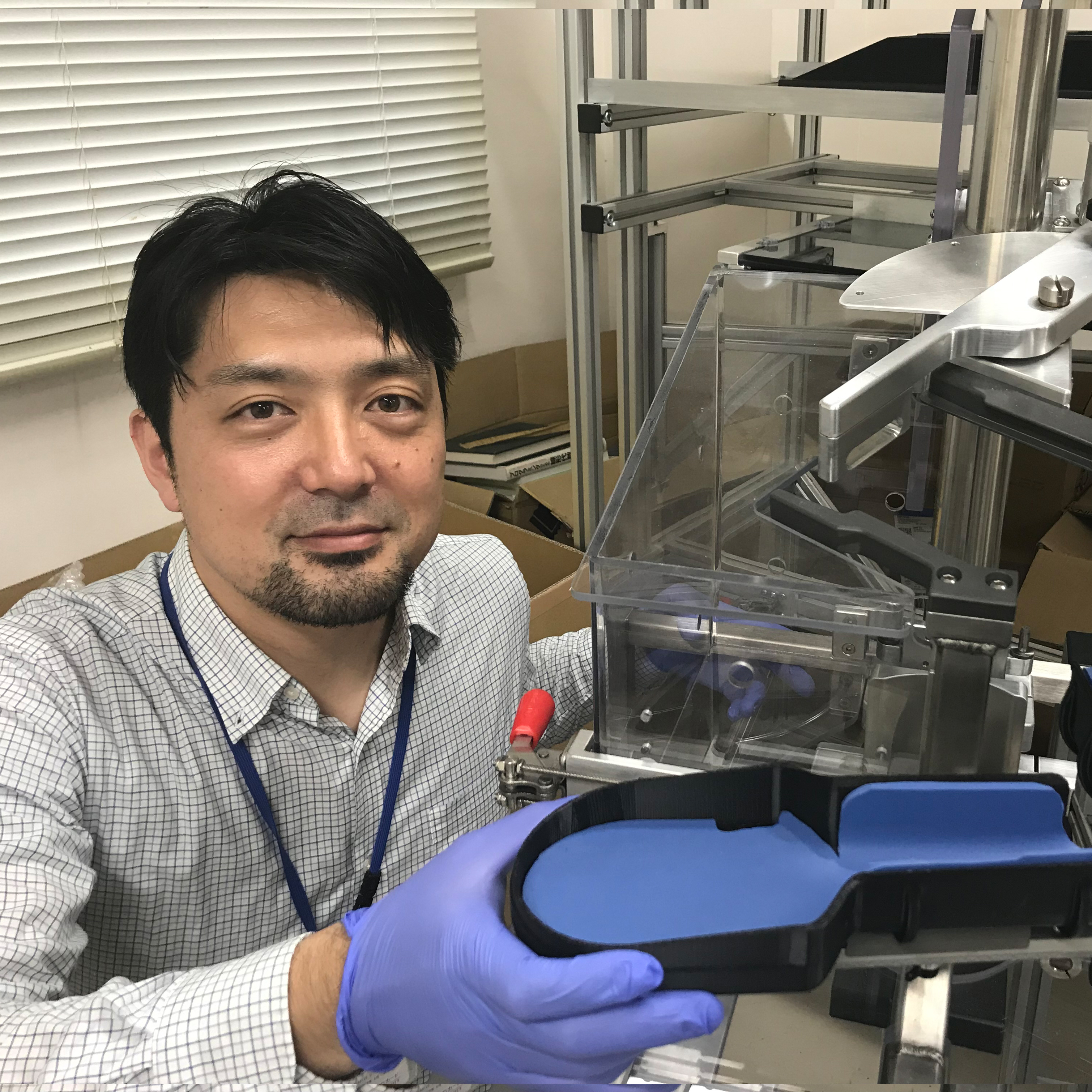
武井 智彦
ヒトをはじめとする哺乳類の中枢神経系では、急性/慢性の障害が生じた場合「通常の適応」の範囲を超えた大規模な神経ネットワークの再構成、すなわち「超適応」が生じることが知られています。それでは一体このような「通常の適応」を超えた「超適応」を引き起こすメカニズムは何なのでしょうか?本研究では1)ブレインコンピューターインターフェース(BCI)を用いた新しい身体性への神経適応過程の研究と、2)「超適応」を再現する人工神経回路モデルを組み合わせることで「通常の適応」とは異なる「超適応」を引き起こす神経メカニズムを明らかにすることを目標とします。
研究組織
| 研究代表者 | 武井 智彦 | 玉川大学 脳科学研究所 准教授 |
| 研究協力者 | 正岡 明浩 | 玉川大学 嘱託研究員 |
A05-11 脳梗塞慢性期に超回復を誘導するための脱抑制の時空間的制御
研究概要
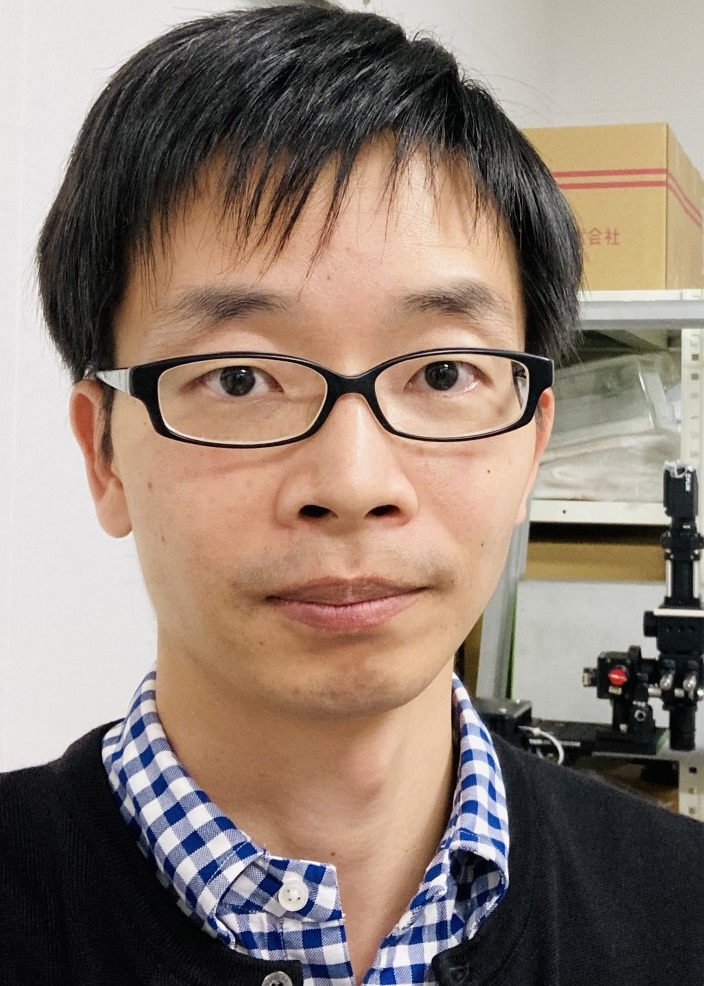
尾崎 弘展
梗塞部位と直接結合関係にある部位ほど脱抑制は長期間持続する。本研究では、「長期間持続する脱抑制が運動機能回復を阻害しているのではないか」という仮説を立て、脳梗塞後の脱抑制現象を適切に制御し、従来の機能回復速度を大きく改善する手法の実現を目指す。
そのために、1.DeepLabCutTMを用いて動物の動きを3次元解析することで実現する運動機能の詳細な評価、2.電気生理学的手法を用いた運動に関連した神経活動の記録、3. 広域高速イメージングによる広範囲の活動変化の記録、4. 光走査による特定領域の神経活動制御。これらの手法を組み合わせて、持続する脱抑制のために回復を阻害している可能性のある神経活動を適切なタイミングで制御し、効果的な機能回復を促す。齧歯類マウスとヒトとの違いにも注意を払いながら、ヒトの治療法へ応用することを目指して、研究を進めていく。
研究組織
| 研究代表者 | 尾崎 弘展 | 同志社大学 大学院脳科学研究科 特定准教授 |
| 研究協力者 | 正水 芳人 | 同志社大学 大学院脳科学研究科 教授 |
| 西村 周泰 | 同志社大学 大学院脳科学研究科 准教授 | |
| 手塚 虎太郎 | 同志社大学 大学院脳科学研究科 大学院生 |
A05-12 空間認知の超適応的変容
研究概要

大須 理英子
脳卒中などによって脳の右半球を損傷すると、視覚機能には異常がなくても、自身の左側の視空間に注意が向かない半側空間無視という症状が現れます。比較的頻繁に見られる症状であるにもかかわらず、有効なリハビリ手段は限られており、また、左に「気づかない」ことによって日常生活に支障をきたすことがあります。そこで、本研究課題では、AR(Augmented reality)とロボットインターフェースを利用した空間への超適応的介入により、半側空間無視の改善に役立つ方法論と空間注意の神経機序に関する知見を得ることを目指します。
研究組織
| 研究代表者 | 大須 理英子 | 早稲田大学 人間科学学術院 教授 |
| 研究協力者 | 平山 健人 | 早稲田大学 人間科学研究科 博士課程学生(助手) |
| 伊藤 ゆうき | 早稲田大学 人間科学研究科 修士課程学生 | |
| 吉田 太樹 | 藤田医科大学 医療科学部リハビリテーション学科 助教 | |
| David Franklin | ミュンヘン工科大学 スポーツ健康科学科 教授 |
A05-13 人為的シナプスコネクトと神経再編の環境制御による超適応機構の解析と創出
研究概要
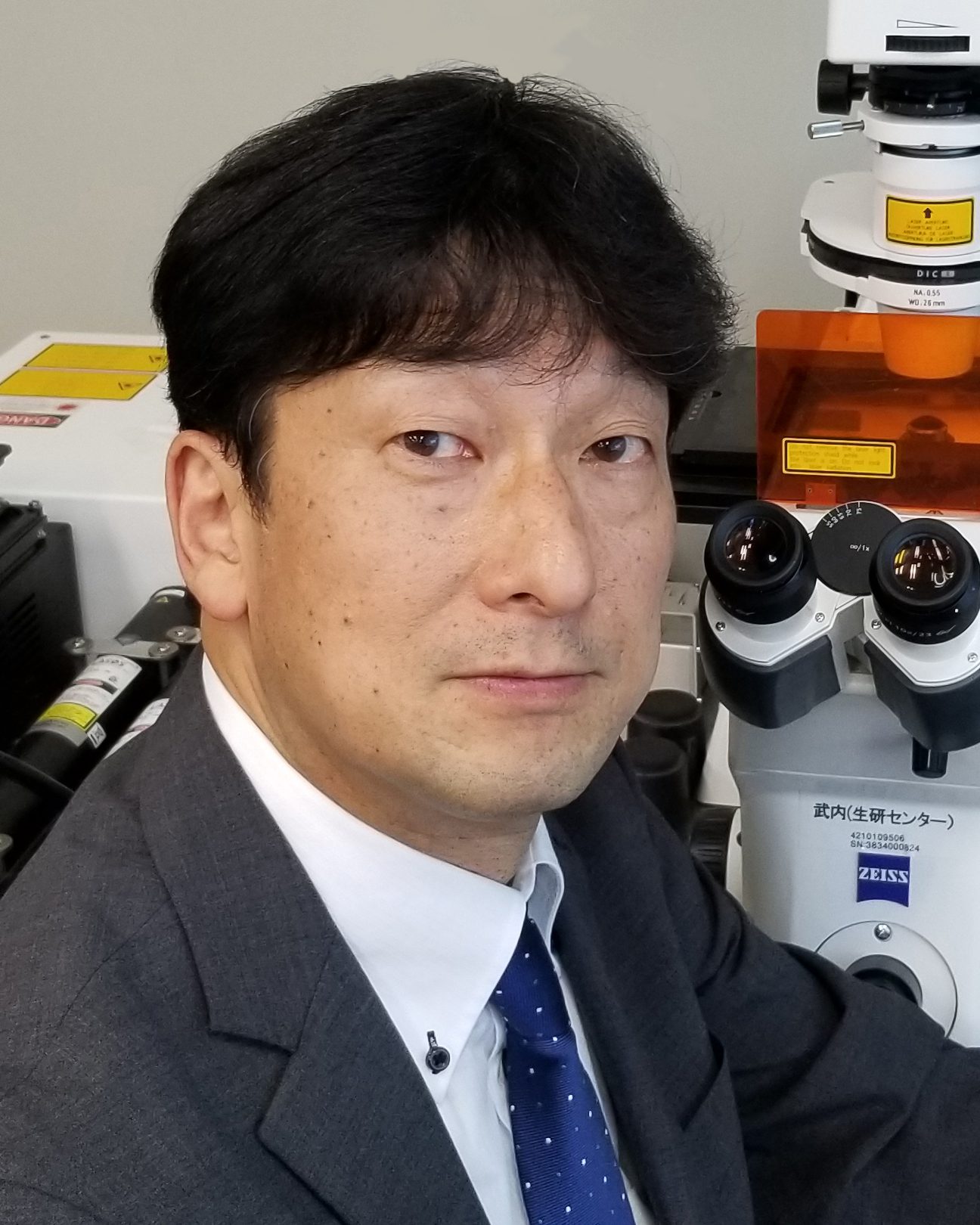
武内 恒成
脊髄損傷は運動生理機能および感覚受容において永続的な機能不全を生じてしまう。これら中枢神経系の損傷に対して、さまざまな機能改善への試みが行われているが、我々は「人為的なシナプス形成コネクター導入」および「神経再生のための微細環境整備」という新しい技術と方法論の導入によって迅速な機能回復を目指している。さらに、その生理的機能回復過程の解析にAI機械学習による解析システムを導入している。人為的な神経組みかえ再編による、超回復および超適応における神経と運動機能の適応過程を解析するシステムを目指し、機能改善の詳細な評価可能なスループット系構築を目的とする。
研究組織
| 研究代表者 | 武内 恒成 | 愛知医科大学 医学部 教授 |
| 研究協力者 | 笹倉 寛之 | 愛知医科大学 医学部 助教 |
| 池野 正史 | 愛知医科大学 医学部 准教授 | |
| 服部 聡子 | 愛知医科大学 研究創出センター 准教授 | |
| 森岡 幸 | 愛知医科大学 医学部 研究技術員 |
A05-14 脳卒中超回復者の脳再構成を静的・動的磁場で誘発される脳波変調で解明する
研究概要
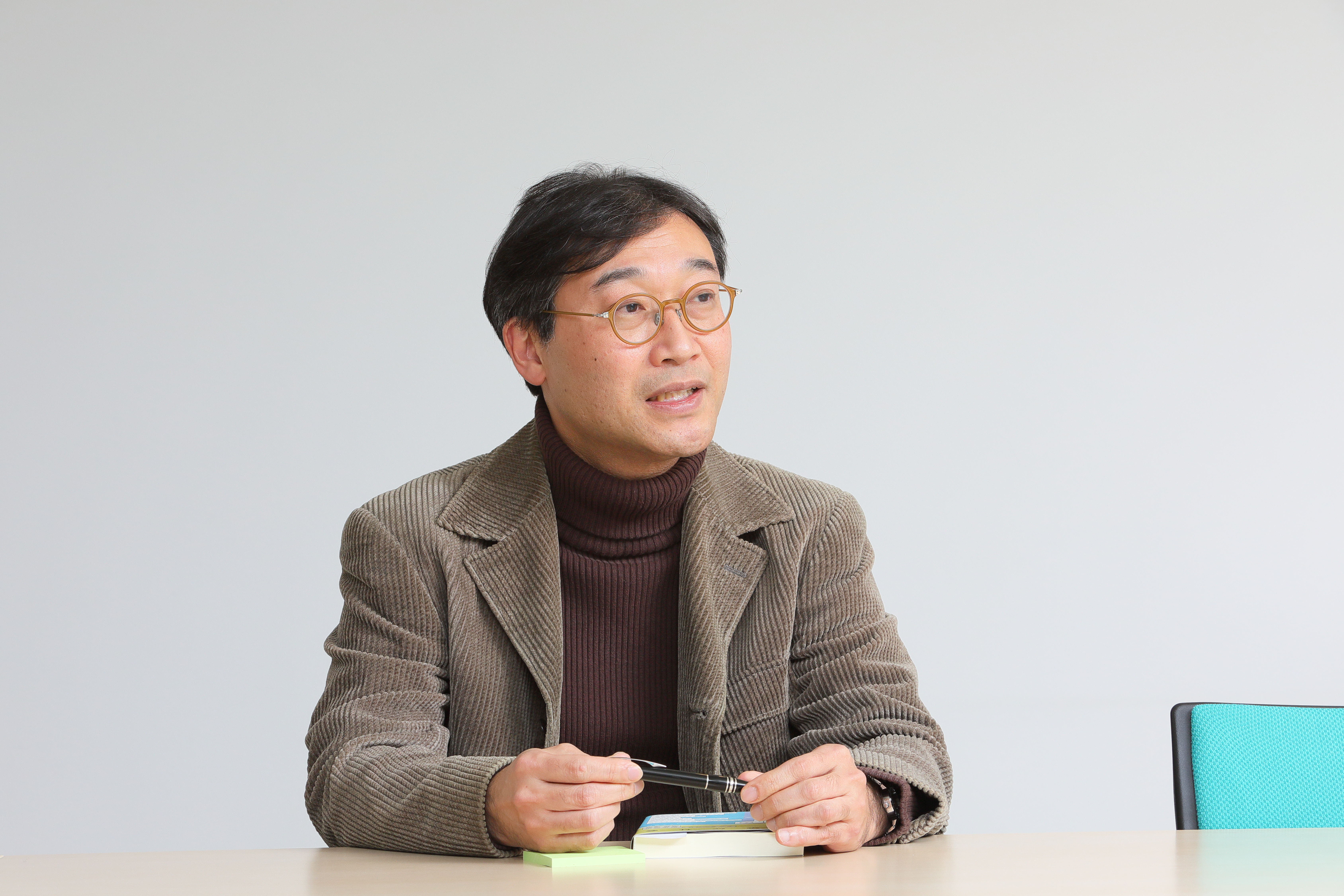
美馬 達哉
脳卒中の「奇跡的治癒」は、超適応の劇的な発現であるという仮説に基づき、このような「超回復」を示す脳卒中後の人々を対象に、神経ネットワークの再構築に着目した臨床研究を行う。本研究では、TMS/tSMS-EEGにより機能的神経ネットワークを測定し、超回復における神経ネットワーク再編成の特異性を明らかにするとともに、健常者では潜在的であるが超適応の過程で活性化する神経結合を探索することを目的とする。
研究組織
| 研究代表者 | 美馬 達哉 | 立命館大学 大学院先端総合学術研究科 教授 |
| 研究協力者 | 芝田 純也 | 新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学療法学科 教授 |
| 小金丸 聡子 | 京都大学 大学院医学研究科 特定准教授 |
A05-15 上肢喪失時における脳の超適応
研究概要

南部 篤
体の一部が事故や病気で失われた場合、脳はどのように適応し障害を乗り越えるのであろうか?手足を失っても、存在しない手足が依然としてあるかのように感じたり(幻肢)、強い痛みを感じることがある(幻肢痛)。さらに脳と身体、特に大脳皮質運動野や体性感覚野は、身体の各部位と1対1に対応している(体部位再現)。手足が失われた場合、体部位再現地図にどのような変化が起きるのであろうか?これらの問題を、ヒトに近い霊長類であり、直接、神経活動を記録することが可能であるサルを対象に、上肢を事故によって失った個体を用いて明らかにする。
研究組織
| 研究代表者 | 南部 篤 | 生理学研究所 生体システム研究部門 教授 |
| 研究協力者 | 畑中 伸彦 | 生理学研究所 生体システム研究部門 助教 |
| 知見 聡美 | 生理学研究所 生体システム研究部門 助教 | |
| Pimpimon NONDHALEE | 生理学研究所 生体システム研究部門 博士研究員 |
A05-16 脳損傷後に大脳両半球で生じる適応機構
研究概要
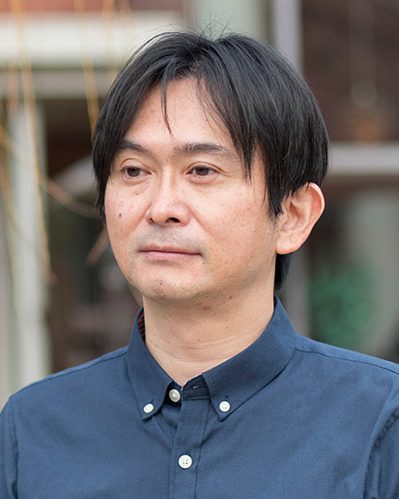
肥後 範行
脳は、脳卒中などによって受けた損傷を代償するためにその構造や機能を変化させる「適応性」を有している。片側内包梗塞モデルマカクサルを用いた私達の最近の研究により、手の巧緻動作の回復後に大脳皮質運動野で代償的な活動変化が生じることを明らかにした。この結果は、損傷が重篤な場合には対側半球運動野の賦活が上昇する点においても、脳卒中患者の知見と一致している。本研究では、内包梗塞モデルマカクを用いて片側内包後脚損傷後の機能代償に関わる大脳半球を決定づける損傷の要因を明らかにする。さらに各半球で生じる、機能代償の基盤となる脳の構造変化を解明する。
研究組織
| 研究代表者 | 肥後 範行 | 産業技術総合研究所 人間情報インタラクション研究部門 研究グループ長 |
| 研究協力者 | 山田 亨 | 産業技術総合研究所 人間情報インタラクション研究部門 主任研究員 |
| 川口 拓之 | 産業技術総合研究所 人間情報インタラクション研究部門 主任研究員 |
A05-17 体性感覚入力欠損後の運動機能回復を支える大脳適応機構の解明
研究概要
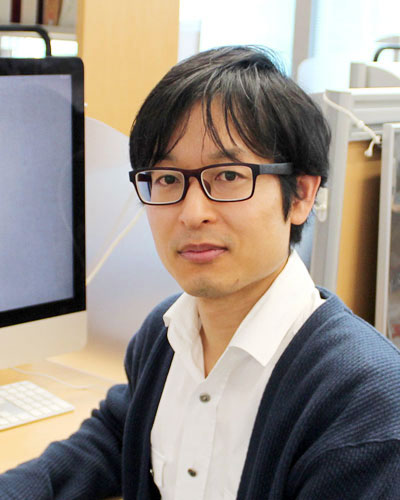
横山 修
体性感覚は運動の実行に重要な役割を果たしている。実際に、末梢感覚神経障害等によって体性感覚情報を受け取れなくなった患者は感覚障害だけでなく運動障害も呈する。本研究課題では、頸髄の後根を切断することによって上肢から中枢神経系への体性感覚入力を選択的に欠損したサルを作製する。このような体性感覚麻痺モデルサルは上肢の運動障害を呈するが、切断から数週間程度の間に運動機能は徐々に回復する。この回復過程における大脳運動関連領野と体性感覚野の皮質脳波を縦断的に記録・解析することによって、運動機能回復を支える大脳皮質活動の適応過程を明らかにする。
研究組織
| 研究代表者 | 横山 修 | 東京都医学総合研究所 脳機能再建プロジェクト 主任研究員 |
