B05研究項目
B05-1 筋シナジーの発現に向けた筋骨格モデルにおけるモジュラリティの運動学習
研究概要

林部 充宏
運動シナジーが人間の運動制御で採用されていることは既知であるが、計算論的に中枢神経がどのようなメカニズムでそれが生成されているかは計算論的数理モデル構築には至っていないのが現状である。本提案ではそれに対するひとつの解決策を示すねらいである。前回の公募研究では関節制御空間においてシナジー発現を実現し、シナジー度合いとエネルギー効率性との相関を深層強化学習により定量的に明らかにした。今回の提案ではさらに一歩進んで筋肉制御空間において運動シナジーの発現メカニズムを明らかにすることで人間の筋活動パターンにおける運動シナジーの役割を計算論的に解明する。またモジュラリティを採用すること自体が運動学習プロセスの実行に有意義であることを定量的に示すことにより、運動シナジー自体の超適応プロセ
スにおける役割の解明につながることが期待される。
研究組織
| 研究代表者 | 林部 充宏 | 東北大学 大学院工学研究科 教授 |
| 研究協力者 | 沓澤 京 | 東北大学 大学院工学研究科 助教 |
| Hannan Ahmed | 東北大学 大学院工学研究科 博士課程学生 | |
| 李 冠達 | 東北大学 大学院工学研究科 博士課程学生 | |
| 福西 彬仁 | 東北大学 大学院工学研究科 修士課程学生 | |
| 杉山 拓 | 東北大学 大学院工学研究科 修士課程学生 |
B05-2 二足歩行運動の超適応メカニズムの神経回路モデル
研究概要

荻原 直道
ヒトの身体は、ヒトが生存戦略として常習的な直立二足歩行を獲得した結果、数百万年という長い時間をかけて、それに適応するように進化してきた。ヒトの身体が二足歩行運動に適応しているという事実は、直立二足歩行を行う上で身体構造の改変が本質的に重要であることを示すばかりでなく、歩行神経系がその身体構造の進化的改変を正しく認識・活用し、二足歩行遂行則を再構成できる適応能力を前適応として有していることを強く示唆している。本研究では、ヒトの進化過程における身体変容に対して、新しい神経制御系を獲得する過程を、神経筋骨格モデルに基づく二足歩行シミュレーションによって解析し、身体構造の改変によって生じる二足歩行の超適応メカニズムを明らかにすることを目的とする。
研究組織
| 研究代表者 | 荻原 直道 | 東京大学 大学院理学系研究科 教授 |
B05-3 発達初期の身体・神経系変容に対する感覚運動情報構造の超適応
研究概要

金沢 星慶
急峻な身体発育や神経成熟が生じる発達初期において,身体障害や神経損傷が生じた際の適応過程で、成人では考えられないような機能回復や機能代償がしばしば生じる.本研究では、新生児期~乳児期に生じた機能障害に対する感覚運動応答や変化に着目した上で,筋骨格身体や神経系の発達的変化や学習則をモデル化することで、発達初期に特異的な機能回復や機能代償過程、すなわち、『発達初期の身体・神経系の変容に対する超適応』に関する理論構築を進める.
研究組織
| 研究代表者 | 金沢 星慶 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 特任助教 |
| 研究協力者 | 國吉 康夫 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 教授 |
| 河井 昌彦 | 京都大学 大学院医学研究科 准教授 | |
| 金 東敏 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生 | |
| 野本 陽平 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生 | |
| 吉田 暁人 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生 | |
| 四宮 大和 | 東京大学 大学院情報理工学系研究科 大学院生 |
B05-4 超適応を可能とする両側運動関連領域における低次元脳機能結合の解明
研究概要

南部 功夫
指や上肢の機能回復を,両側(両半球)に存在する複数の運動関連領域よって実現するメカニズムは「超適応」の代表例である.しかし,両側運動関連領域による冗長性をどのように利用しており,どの程度の冗長性があるか等,詳細な原理は解明されていない. そこで,本研究では超適応の基礎となる両側運動関連領域の冗長性および相互作用を解明することを目的とする. 特に,両側運動関連領域の結合は低次元空間上に表現されているという仮説を脳波等のヒト脳機能イメージングデータにより検証する。
研究組織
| 研究代表者 | 南部 功夫 | 長岡技術科学大学 大学院電気電子情報工学専攻 准教授 |
| 研究協力者 | 和田 安弘 | 長岡技術科学大学 大学院電気電子情報工学専攻 教授 |
| 横山 寛 | 自然科学研究機構・生理学研究所 神経ダイナミクス研究部門 特任助教 |
B05-5 部分ダイナミクスの再利用を行う運動学習モデルの筋シナジー再構成への拡張
研究概要

小林 祐一
人の身体または脳に部分的機能不全が起きた際には,過去に獲得した神経回路を再利用して機能を適応的に回復させることができる.このような適応過程を説明する運動学習モデルを提案する.これまでに得られている運動システムの部分的な依存関係の変換を推定する運動学習モデルではフィードバック制御機構を基礎としていたのに対して,本研究では,フィードフォワード制御を獲得する過程にも着目する.フィードバック制御における係数情報の変換の推定に加えて,フィードフォワード項の変換を考えることで,筋シナジーのようなすでに獲得された運動制御情報を再利用する過程を説明することを目指す.
研究組織
| 研究代表者 | 小林 祐一 | 静岡大学 工学部機械工学科 准教授 |
| 研究協力者 | 中村 壮太 | 静岡大学 大学院総合科学技術研究科 大学院生 |
| 松浦 太星 | 静岡大学 大学院総合科学技術研究科 大学院生 | |
| 間宮 陽希 | 静岡大学 大学院総合科学技術研究科工学専攻 修士課程 | |
| 和田 泉 | 静岡大学 工学部機械工学科 学部4学生 |
B05-6 眼と身体の新しい関係への適応の階層的解明
研究概要

北崎 充晃
バーチャルリアリティを用いて,「通常とは異なる視覚-身体関係」を作り出し,それによって人の知覚と行動がどのように変わるか,その可塑性を明らかにすることを目的とする。本研究では,通常とは異なる環境として「眼と身体の関係」を操作し,中長期の順応により人の認知行動の可塑性を「意識的行動戦略の水準」,「無意識的行動の水準」,「知覚の水準」で心理物理実験により明らかにする。
研究組織
| 研究代表者 | 北崎 充晃 | 豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 情報・知能工学系 教授 |
B05-7 ヒト静止立位の微小転倒に随伴する脳波応答に基づく姿勢制御脳内メカニズムの解明
研究概要
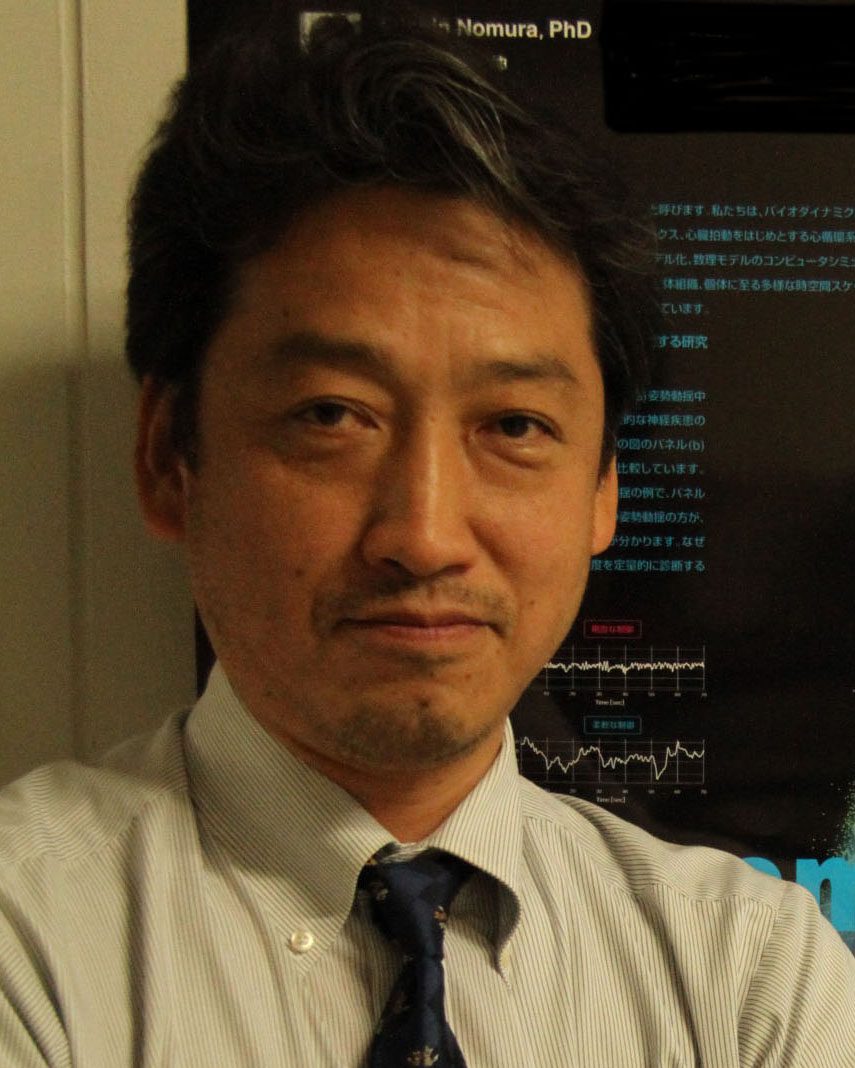
野村 泰伸
静止立位姿勢の不規則な動揺は、微小転倒とそこからの微小回復過程の繰り返しパターンで構成されます。微小ではあるものの、繰り返しの性質を利用して、外乱が一切無い静止立位維持に関わる脳波動態を定量化し、その制御論的意味を明らかにすることを目指します。
研究組織
| 研究代表者 | 野村 泰伸 | 大阪大学 大学院基礎工学研究科 教授 |
| 研究協力者 | 中村 晃大 | 大阪大学 大学院基礎工学研究科 学振特別研究員PD |
| 鈴木 康之 | 大阪大学 大学院基礎工学研究科 講師 | |
| Matija Milosevic | 大阪大学 大学院基礎工学研究科 助教 | |
| 中澤 公孝 | 東京大学 大学院総合文化研究科 教授 | |
| 佐古田 三郎 | 国立病院機構刀根山医療センター 名誉院長 | |
| 遠藤 卓行 | 国立病院機構刀根山医療センター 医師 |
B05-8 超適応としての高次脳機能:無限定環境へのプロアクティヴ・アウトリーチ原理の探究
研究概要
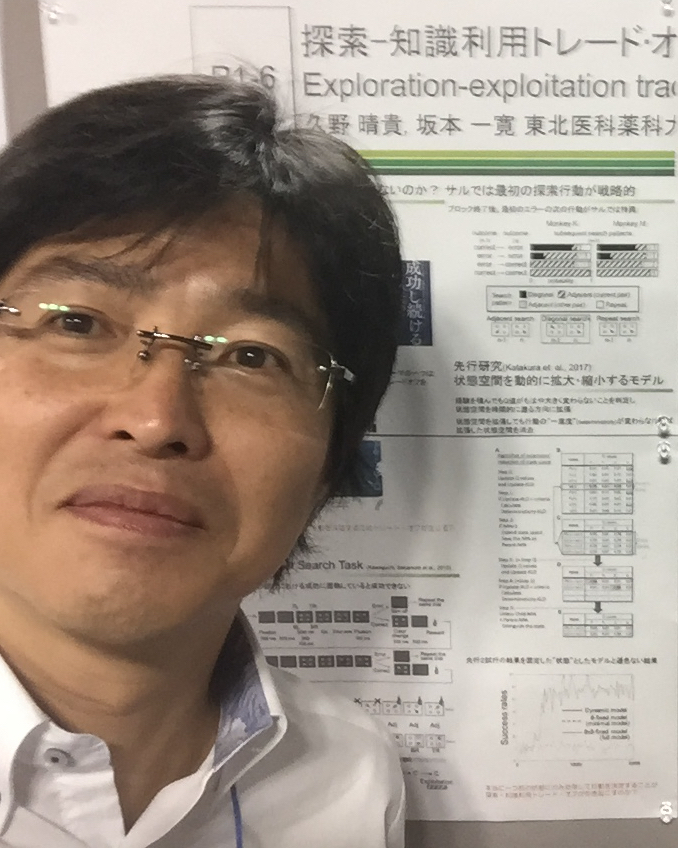
坂本 一寛
「一寸先は闇」のこの世の中、座したままでは死を待つのみ。経験と知恵を振り絞り闇に切り込んでこそ活路が開く。何が起きうるか確率空間すら規定できない環境を無限定環境と呼ぶ。そのような環境への適応原理の一つとして、我々はこれまで、経験飽和度と行動決定一意性を基準に確率空間・状態空間を動的かつ自律的に規定する強化学習モデルを構築した。しかしながら、積極的に環境への見方を変える原理は得たものの、積極的かつ戦略的に環境に向けて働きかける原理の解明には至らなかった。そこで本提案では、無限定環境へのプロアクティヴ・アウトリーチ(積極的働きかけ)原理の解明を目的とする。具体的には、動的状態空間強化学習モデルを発展させ、高次脳機能、特に高次運動野/前頭前野のモデリング、つまり、これら諸領野が担う機能を引き出す様々な課題を学習するモデルを構築し、それを通じて行動計画策定の原理、順序行動発現の原理を明らかにする。これらの研究は、計画が立てられない、家電製品を適切な順序で操作できない等の高次脳機能障害の神経基盤の解明と治療法探索に貢献できる。
研究組織
| 研究代表者 | 坂本 一寛 | 東北医科薬科大学 医学部 准教授 |
| 研究協力者 | 松坂 義哉 | 東北医科薬科大学 医学部 教授 |
| 中村 正帆 | 東北医科薬科大学 医学部 准教授 | |
| 虫明 元 | 東北大学 大学院医学研究科 教授 | |
| 小山内 実 | 大阪大学 大学院医学系研究科 教授 | |
| 洞口 学志 | 東北大学 大学院医学研究科 博士課程学生 |
B05-9 ニューロフィードバック注意機能訓練における脱抑制回路の多様性と運動制御への寄与
研究概要
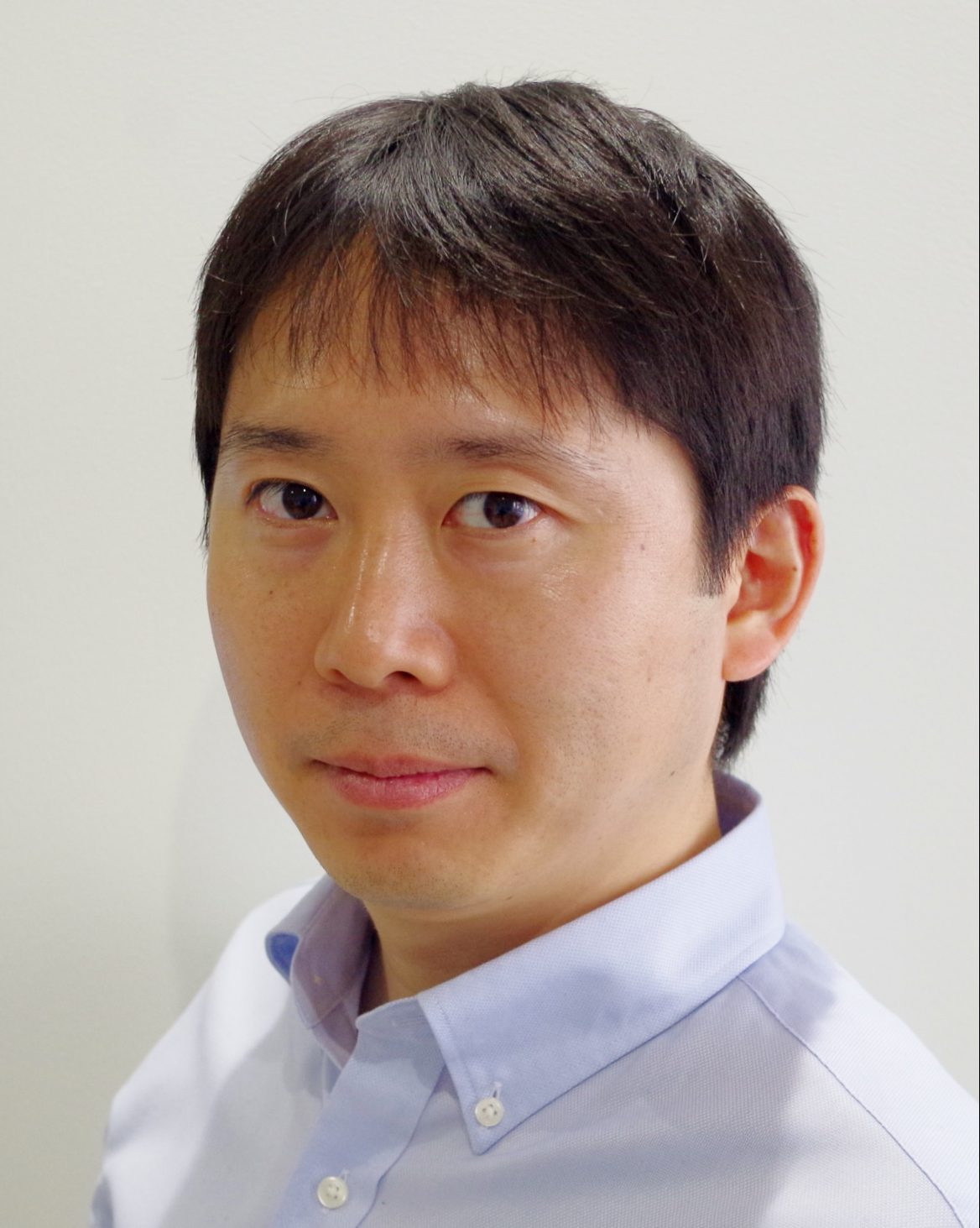
櫻田 武
本研究では,これまで確立してきた,低次感覚野活動に基づくニューロフィードバック技術を用いて,若年者・高齢者の注意機能向上に有効なテイラーメード訓練システムを確立する.このシステムによって,個々人の認知機能特性に応じて,最も獲得しやすい神経回路の賦活が促され,最終的に注意や運動機能が向上することを示す.さらに,訓練によって獲得される神経回路の多様性をモデル化し,効率的な介入プロトコルの提案を試みる.
研究組織
| 研究代表者 | 櫻田 武 | 成蹊大学 理工学部 准教授 |
| 研究協力者 | 田口 俊輔 | 成蹊大学 理工学部 学部学生 |
| 中島 大輔 | 成蹊大学 理工学部 学部学生 | |
| 林 優里 | 成蹊大学 理工学部 学部学生 |
B05-10 探索的適応を生み出す脳内ネットワーク:メタ強化学習に基づく脳機能モデリング
研究概要

植山 祐樹
自転車の乗り方などの技能の獲得や新しい環境に適応する際,我々は試行錯誤的に行動を繰り返すことで,行動の結果として得られる限られた情報を手掛かりに最善の方策を探索します。本研究では,そのような探索行動に基づく適応機構を「探索的適応」と定義し,超適応の一端を担う脳の計算機構として捉え,それを実現する神経基盤の解明を目的とします。そのために,探索的適応をメタ強化学習と呼ばれるアルゴリズムによってモデル化し,視覚運動学習と呼ばれる基礎的な実験課題を用いたfMRI実験を行うことで,計算論および脳機能画像解析の両面からアプローチします。
研究組織
| 研究代表者 | 植山 祐樹 | 防衛大学校 機械工学科 准教授 |
| 研究協力者 | 今水 寛 | 東京大学 大学院人文社会系研究科 教授 |
| 井澤 淳 | 筑波大学 システム情報系 准教授 |
